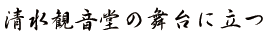Q: 月の松を復元された経緯をお話し頂けませんか。清水観音堂の周辺も、ずいぶん整備されたようですが。
まず復元したいという思いには、江戸時代の風景を再びという気持ちがありました。150年ぶりに江戸時代に近い景観を取り戻したい。それが出来るかはまったく分からなかったんですが、今に至って何とか月の松を復元出来ました。江戸時代の浮世絵とまったく同じ風景を見る事は出来ませんが、復元された月の松の事を聞いて見に来られる観光客の方もいらっしゃいます。信者さんの数は変わりませんが、観光で来られる方は二割程増えました。二割程と言っても20万人、30万人程ですから大変な数です。また不忍池の辯天様が、月の松の輪から見えますので写真を撮る方が多くおられます。お堂の周囲には永らく鬱蒼とした雑木林がありましたが、近年整備して頂いて不忍池が望めるようになりました。
Q: 明治時代には博覧会等もあり、不忍池は埋め立てられていたとの事ですが。復元された月の松は元はどこにあったのでしょうか。
そうですね、すべてが埋め立てられたわけではないんですが、一時は競馬場になったり、博覧会が開かれたりしましたので、池自体も少し小さくはなりました。月の松も明治時代初期までは不忍池の端にあったようですが、台風で倒れてしまいました。その当時は月の松があった地は国の管轄地でしたから、そこに復元する事も出来ずにそのままになっていました。(右段に続く)

境内に植えられた控えの松
Q: 復元された月の松は、どのようにして作られたのですか。
私が清水観音堂の輪番となって10年程ですが、もしも月の松が復元できればと知り合いの造園業者さんに聞いてみたら、まあなんとか形だけは整えることができるのではとの事で思い立ちました。江戸時代末期には月の松を作る技術があったそうです。木を殺さないように真ん中の芯を少し抜いて丸くして、本来引力で垂れ下がってしまう枝を丸くしていたようです。今でもその技術を持った方が千葉の方におられますが、費用の兼ね合いもあり、知り合いの造園業者さんに頼んで5年6年程前から丸くする作業に取りかかってもらって、約3年半程要しました。4本程作ってもらいましたが、2本は枯れてしまいました。上手く出来た2本のうちの1本が現在の月の松で、もう1本は控えの松として境内に植えられています。

信者さんから寄贈された月の松の盆栽
Q: 復元される際には、歌川広重の浮世絵を参考とされたのですか。
参考にはしましたが、安政3年(1856)から5年(1858)に描かれたと言われる歌川広重の江戸百景は、安政の大地震(1854)の復興のために制作されたと言われています。江戸百景の浮世絵を江戸に来られた人に買ってもらって、これを財源にして江戸を復興しようというのが当初の構想だったようです。ですから当時は、大地震の後で当時の街並みも損なわれていたかもしれません。この度復元しました月の松も3月11日の東北地方太平洋沖地震の後に植えましたので、そのような気持が私どもにもあり、出来れば復興に一役買えればという気持から、浄財を頂いて被災地へお持ちしたりしています。