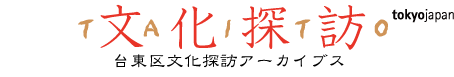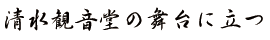歌川国貞「中古倭風俗旧幕大藩の姫君上野清水御花見之図」(寛永寺長臈浦井正明氏蔵)

真如院住職 清水観音堂輪番の大多喜義慶さん
東叡山寛永寺 真如院住職、清水観音堂輪番の大多喜義慶さんにお話しを伺いました。本インタビューは平成26年(2014)7月に取材しました。
Q: 江戸時代には上野公園一帯は東叡山寛永寺さんの境内だったとのことですが、清水観音堂はどのような位置付けだったのでしょうか。
寛永寺は徳川家の菩提寺でしたが、清水観音堂は一般の方のどなたでもお参り出来るお堂として建てられました。創建当初は摺鉢山に建っていましたが、寛永寺の本堂を造営する際に現在のこの地に移されました。
Q: このお堂は、元は寛永寺さんの山門の外にあったのですか。
いえいえ、山門は元は現在の松坂屋百貨店がある黒門町あたり(現在の上野2・3丁目)にありましたから、山門から上がって最も近く良い場所にあり、どなたでも参詣出来ました。その先は一般の方は容易にはお参り出来ませんでしたので。清水観音堂は慈眼大師天海大僧正自ら建てたお堂です。私財を投じて造り、本尊は平安時代の比叡山の高僧の恵心僧都(えしんそうず)作と伝えられる千手観世音菩薩(せんじゅかんぜおんぼさつ)を京都の清水寺から頂いてきました。(右段に続く)
ご本尊の千手観世音菩薩は、元は平家物語にも語られる謡曲「盛久」に謡われた武将平盛久がお守りしてたのですが、源平合戦で敗れて京で捕らえられて鎌倉へ送られ、死刑の裁きを受けて鎌倉の由比ガ浜で打ち首になる予定でした。ところが、盛久の頸めがけて振り下ろされた刀は折れ砕け、また源頼朝の正室北条政子の夢枕に僧侶が現れて平盛久を殺してはいけないと言ったため難を逃れました。盛久の打ち首のその時に京都の清水寺に祀っていた千手観世音菩薩が倒れ、その手が折れた事から盛久受難の身代わり観音として大変厚く信仰されました。この観音を天海大僧正がここ清水観音堂に頂いて本尊とされました。京都清水寺貫主の森清範さんは、元は京都清水寺の奥の院にあった本尊であろうとおっしゃっています。おおよそ千年程の古い仏様ですから重要文化財、国宝クラスであろうと思われますが、秘仏ですので詳しい調査は未だ行われていません。
平盛久が難を逃れた刻(とき)が午の年午の日午の刻であったという事で、年に1回立春を過ぎた初午の日に本尊を御開帳して、一般の方のどなたでもお参り出来るようにしています。来年(2015)は2月11日になります。
Q: 京都清水寺と合同で催される行事はありますか。清水観音堂の舞台は、京都清水寺の舞台に倣っているのですか。
清水と名付けられた寺は国内に九十九寺あり、合同で行う会を催しています。清水観音堂の舞台は、京都清水寺の舞台を縮小して造られています。舞台から望む不忍池には辯天堂があり、ここには琵琶湖竹生島の宝厳寺から勧請(かんじょう)された八臂大辯財天(はっぴだいべんざいてん)を本尊としています。天海大僧正は、比叡山と京都、そして琵琶湖と見立てて東叡山寛永寺を造ったのでしょう。
Q: 江戸時代の浮世絵師歌川広重が描いた浮世絵には不忍池が見えていますが、ここを琵琶湖になぞらえたという事ですか。
そうですね、京都の清水寺からは琵琶湖は見えないのですが、これらを凝縮して造ったのでしょう。清水観音堂と辯天様は一般の方はどなたでもお参り出来るお堂です。辯天様が造られた当時は、今のように陸続きではなくて島でしたので船で渡らないとお参り出来ませんでした。

真如院住職 清水観音堂輪番の大多喜義慶さん