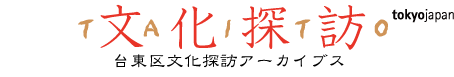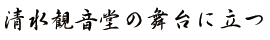清水観音堂書院に掛けられた壮大な東叡山寛永寺を物語る図会(寛永寺清水観音堂蔵)
Q: 清水観音堂は、国の重要文化財に指定されているとの事ですが。本堂は、元から朱塗りだったのですか。
本堂は朱塗りでした。江戸時代の建立当時と同じように復元した建物ですから、重要文化財に指定されています。堂内も現在は極彩色ですが、解体・修理工事の際に黒く煤けていたのを洗って当時の色が蘇りました。書院は、昭和8年(1933)頃の創建だったかと思いますが、当時の著名な建築家伊東忠太氏が設計したため、今でも建築関連の方々が後学のために見学に来られます。
Q: 上野公園内も取材していますが、近くには幕末の上野戦争で明治新政府軍と戦った彰義隊の墓所等もありました。この一帯も焼失してしまったのでしょうか。
堂内にも上野戦争の光景を描いた絵馬が掛けられていますが、大砲を撃ち込まれたりした最も激戦の地でしたので多くは焼失しましたが、清水観音堂はなんとか難を逃れて保つ事が出来ました。しかし、一時は政府に没収されて管理出来ずに荒れるに任せるような状態でしたが、本尊や本堂は何とか無事でした。今も上野戦争当時に飛び交ったであろうと言われる砲弾が絵馬と共に堂内に掛けられており、現在これらについても調査されています。
Q: 上野の町もずいぶん変わってしまいましたが、江戸時代のお参りのコースはどのようになっていたのでしょうか。
松坂屋百貨店のあたりからの階段は古い図会等にも描かれていますが、現在でも江戸時代からの面影を残しています。上野駅は、明治15年(1882)に寛永寺の子院跡を東京府より借り受けて用地として明治16年(1883)に開業しました。ですから、元はお寺があった所でした。その後に山手線が開通したりして、さらに削られてしまって今の形になりました。ですから、本来の地形は浅草の方へとずっと続くなだらかな傾斜地で周辺にはお寺も多くありました。現在の東京文化会館や国立西洋美術館がある所にもお寺が建ち並んでいました。山門は元は現在の黒門町あたり(現在の上野2・3丁目)にあって、そして広小路(現在の上野広小路界隈)がありますからね。広小路は火事を防ぐための広い道路の事ですから、ここからでなければ参拝客は上がって来られませんでした。そして寛永寺の奥は将軍家の墓所ですから一般の方は近づく事が出来ませんでしたし、夕方になると一般の方は外に出されてしまいました。ですが、昼間はどなたでも清水観音堂や辯天様はお参りが出来るようになっていました。
この周辺はあまり変わっていません。このお堂自体は400年近くこの場所にあるわけですから、下の道路等もほとんど雰囲気は変わっていないと思います。昔は木がもっと少なかったので、この辺からも不忍池が見えたのですが、公園になりました時に色々な木を植えましたので、現在では少し見えにくくなってしまいました。(右段に続く)
Q: 上野公園は、桜の名所としても名高いのですが、いつ頃からでしょうか。
天海大僧正は、東叡山寛永寺が開かれた際に吉野から桜を移植して桜の季節には桜が満開になる場所にしたようです。当時から花見の季節には一般の町人の方たちも多く上野へ来て花見をして食事をしたりしていたようです。昔から、そのように楽しめるテーマパークのような場が造られていたようですが、それが今日にも続いています。やはり桜が咲けばどうしても上野という地名が出てきますね。
Q: どのような方々がお参りに来られるのですか。
脇本尊に子授けと子育ての観音様がおられます。ですから、江戸時代から子供を望まれる方や子育てに悩まれる方がお参りされる観音様として大変多くの信仰を頂いています。清水観音堂では毎月17日が縁日になっていて、ご祈祷をしております。その他には、初午が年に一度の大きなお祭りで、2月の最初の午の日が縁日になっていますので、信者さんも大変多く参られます。普段でも、観光客の方々が世界各地からお出でになります。上野へ来られる外国人観光客にとって、清水観音堂は必ず立ち寄るルートのひとつとなっています。
その他、9月25日には人形供養をさせて頂いております。江戸時代には子供に恵まれた際に無病息災を願って身代わりに人形を奉納してきました。これが現代まで伝わって愛でてきた人形を供養するようになりました。人形は、愛着もあり、魂が伝わるような面もありますから、こちらに持って来られてご供養して魂を抜いて差し上げています。雛(ひな)人形等もありますし、ぬいぐるみの人形等も多くあります。毎日、私がご祈祷していますが、不在の際にはご祈祷するまでの間、ご本尊様の横にお飾りしてあります。この供養の集大成として9月25日に大きな人形供養の法要をさせて頂いております。
Q: 海外からの観光の方を多く見掛けますが、掛けられている絵馬にも外国語のものが多いようですね。
普段は、お参りされる方の五割程は海外の方ですね。日本語が聞こえない時も結構あります。中国や台湾等の国にも観音信仰がありますから、皆様ここに来られてお参りされています。他には欧米の方たちも多く来られます。ですから、英語の他にも多言語で書かれた冊子類を用意しています。御守り等にも英語バージョンがありますので、これをお見せして、ナンバーが書かれていますから、この数字はこのような意味ですと説明できるようになっています。絵馬については、海外の方も理解して頂いていて、願い事があれば書いて掛けていかれる方もいますし、また珍しいからと持ち帰られる方もおられます。外国語で書かれた絵馬が掛かっていますと、それを他の海外の方が見掛けて、自分もという事で書かれていかれる方も多くおられます。