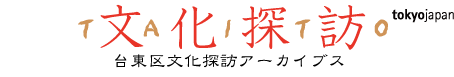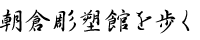Q: ご家族はどのように暮らされていたのですか?
家族がどのような生活をしていたかはよくは分かりません。この和室の建物の手前から寝室、朝倉のプライベートルーム、そして茶の間だったという事は分かっていますが。郷里にはまだ一族がいましたし、どんどん忙しくなっていきましたから、郷里に帰るという事も難しくなっていたのですが、やはり育ったところ、大分県を懐かしく、大事に思っていました。晩年になって、文化勲章を受けて帰郷するのですが、大変嬉しそうな顔をした写真も残っています。
Q: 庭の造りや由来について教えて下さい。
この中庭は、「五典の水庭」と名付けていますが、朝倉が意識して造った庭だと思います。これは四方造りで、どこからでも観られる回廊式です。どこも正面であって、また、どこも正面ではないという、そのような庭の造りです。日本庭園では、部屋があり、廊下なり縁側があって、ちょうど額縁の中に収まるように美しい庭の景色が見えるように造られていますが、これはその一方向だけでなく、どこからも見えます。これは言ってみれば朝倉の仕事と繋がっています。彫刻は360度から見えるように作っていますから、この庭は、やはり彫塑家の思い付いた庭の造りだと思われます。たとえば、今はこの部屋からは畳に座って観ていますが、この畳に座った目線から庭がきれいに見えます。それで、また廊下から観た時には、立って歩いている目線ですから、そこからまた上手く広がりができています。また、板の間の椅子に座って観るというような構造に成っています。そのように意識的にこの庭を造っています。今日では例えばコンピュータグラフィックスで3次元のものをグルグル回して見るというような事ができますが、人はそのようにして様々な物を見ているわけです。(右段に続く)

朝倉は弟子を指導する時に、デッサンをしないようにと言っています。彫刻には彫刻のためのデッサンの方法がありますが、朝倉は、人間は3次元でものを把握する力がある、それを2次元にすると、そこで一回停滞する事になるから、最初から粘土でデッサンするくらいのつもりでやりなさいと言うような指導をしています。そのような3次元に対する感覚が、この庭に注がれているのではないかと思います。

Q: 四季によって表情が異なるのですか。
樹木や花が庭の表情を表しますが、1月の梅から12月の山茶花(サザンカ)まで、白い花をつける樹木ばかりを選んで植えています。例えば5月には卯木(ウツギ)の花、卯の花という低木ですが、これが庭一面に白い花を着けます。白というものは、純白という程に清らかなもの、純粋なものと考えて、それを庭に満たす。けれども、満ちるは欠くる事ですから、一本だけ夏は赤い花をつける百日紅(サルスベリ)を植えています。自然の中にある白の美しさを強調する魅力があります。
この部屋は、朝倉の自室だったところです。船底天井になっていて、これは神代杉なんですね。そういう高級な材料を使う一方、煎茶道具棚も朝倉自らが考案したものですが、特に上等というものでもありません。こういうものを唐ものの棚と何箇所か組み合わせて置き書院を造っています。障子の桟は、細工物です。胡麻竹を一度崩して、中に骨を入れて四角い竹にしています。このような非常に凝ったものと、日常的に自分が発想したもの、たとえば大胆に付けたはたきの柄等と、面白い構成をしています。この場所が轤(ろ)ですから、朝倉はこの辺に腰掛けて、夏場はこの柱にもたれて池を観る、そのような写真も残されています。

煎茶道具棚

煎茶道具棚