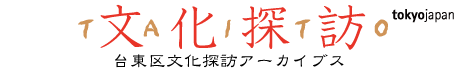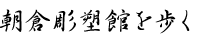朝倉彫塑館研究員の村山万介さん
台東区立朝倉彫塑館研究員の村山万介さんにお話しを伺いました。(2009年2月2日に取材しました。)
Q: 朝倉彫塑館設立の由来を教えて下さい。
村山 : ここは昭和10年に完成した朝倉彫塑館のアトリエです。今は朝倉彫塑館といっていますが、当時は朝倉邸であり、朝倉彫塑塾という彫刻の専門学校でもありました。実際にここには今たくさんの朝倉作品が並んでいますが、これらはすべてブロンズ像ですけれども、最初は粘土で作るんです。粘土でこさえて、完成します。そのままではすぐ壊れてしまうので、すぐに石膏で型を取りまして、石膏原型というものに移し換えます。その石膏原型を基にまた型を取って、今度はブロンズにします。ブロンズとは鋳物ですから、鋳物の鋳型を作って溶けたブロンズを流し込んで、このようなブロンズ像になっていきます。これらの工程を簡単に省いて言いましたが、実際には150工程ぐらいもある非常に複雑な、専門の例えば石膏屋さん、それから美術鋳造の職人さんがこうやって仕上げていくわけです。
朝倉文夫はこの場所で粘土の像を作るという仕事をやっていました。また同時に、朝倉彫塑塾の門下生に指導を行っていました。その現場がここです。この建物は、構造的にはRC構造です。鉄筋の建築で、もしそれがそのままであれば、この部屋は打ちっぱなしの灰色の冷たい箱であるわけですけれど、今は薄い茶色の壁ですが、これは真綿ですね。真綿をほぐして染めて、今では詳しいことまではよくは分からないのですが、それを貼り込んでいったというか、塗り込めていったというか、そういうものでコンクリートの壁に温かさを出しています。この家全体を朝倉文夫自らが設計していますけれども、非常に細かいところ、材質等も含めて朝倉が指示をしています。非常にこだわって、凝りに凝って造った建物、その中のこのアトリエという風に見て頂ければと思います。
Q: 代表的な作品について教えて下さい。
これは「墓守」という作品で、朝倉文夫の代表作のひとつです。制作年は明治43年(1910)、第四回文部省美術展覧会、略して文展に出展して、最高賞を受賞した作品です。この作品は朝倉の比較的若い時の作品のひとつとなりますが、生涯の作品の中でも大きな意味を持っています。それは非常に作風の転機となった作品なんですね。朝倉は明治40年(1907)に東京美術学校(現東京藝術大学)を卒業して、明治41年(1908)に第二回の文展でデビューをするわけですが、その卒業年次であるとか、その数年間というものは、すぐ脇に「進化」という卒業制作が並んでいますけれども、例えばそういうものをご覧になっても、また、この作品は残っていないのですがデビュー作である「闇」という作品。今は竹橋の近代美術館が所蔵している「山から来た男」。こうしたものは非常に主題性の強い、タイトルもちょっと文学臭の強い、そうしたものだったんですね。具体的に何かって言うと、頭の中で考えて、主題を考えて、それに沿って造る。
卒業制作の「進化」というのは、言ってみればその当時の進化論ですね。ダーウィンの「種の起源」というのが翻訳されて非常に影響力を持っていて、それが自然科学の分野だけではなくて文学であるとか美術の方にまで影響があって、そこの中で作られたのが「進化」という作品です。つまり、主題というものがまずあって、頭の中でポーズから何から考えて造っていた。そういう時代がまずあったわけです。今までは頭の中で考えていたけれども、実際にモデルをおいて作ったら、非常にすらすら出来て、今風に言えば頭でっかちの仕事じゃなくて、やはり彫刻らしい仕事、表現らしい表現がそこでできた。で、自分がこれからこういう風にやったほうがより彫刻というものの表現に近づけるのではないかという風に朝倉は選ぶんですね。つまり頭で考えた、不自然なものではなくて、自然にあるものを自然のままに写すということを、それが写実という仕事の中で大変大事なことなんじゃないかということをこの作品がきっかけになるんです。
この作品の特徴で言えば、写実です。物の形、姿をきちんと置き換えていくという、そういう美術の古典的な仕事ですけれども。これは男性像ですね。朝倉文夫は後になって言いますけども、頭の中だけで考えて造っていた時代の制作というのは自分でも非常に辛かった、苦しかった。だけれども、この「墓守」を作った時には、実際に美術学校に通っていた時からよく見た、谷中のお墓の守をしている墓守のおじいさんが、そのおじいさんの面差しが非常に彫りが深くて、なんとも魅力があって、一度アトリエに来てもらえないか、で「墓守」のモデルのこの人は名前までわかっており、「田辺半次郎」という墓守のおじいさんですけども、その人にアトリエに来てもらって、お弟子さんが将棋を指しているのを、こうやって見ている所をそのまま造っていったんだと。で、女性像も造ります。女性像を造る時には、朝倉文夫は非常にきめ細かいというんですかね、特にヌードの作品とか多いですから、女性を作るときは非常にきめの細かい仕上げをします。一方、男性像を造る時というのは、粘土のつけ方というのが大きいというんですか、激しいっていいますかね、大きいリズムがあります。例えばこの半纏の垂直線。これはこうまっすぐこう下りていますけども、こういうのもよく見ると、一気に手でつけていって撫で下ろしたのをもう一回手のひらでザッと上に撫でるようなのが見てとれます。後ろに回りますと、手を組んでいますけれども、その手もよく見るとヘラでグワッとかきとって、もうそのまま、仕上がってんのかな、仕上がってないのかなという状態で終わっているんです。でもそれは要するに彫刻表現にとって朝倉がこれでいいんだ、これで十分な意味合いを持っている。質と量、それからバランスというものを持っているというので、決定しているわけですね。それがやはり迷い無く造っていったところのひとつの結果ではないかと思いますし、「墓守」という作品が朝倉の代表作になったひとつの理由かなと思います。
Q: 彫塑と彫刻の違いは何でしょうか?
彫刻と彫塑というのは技術の問題なんです。技術だったり素材がまったく違うことがあります。一般的には両方含めて彫刻ということの方が多いです。現在ではもっと、例えば立体作品という風に言ってしまったり、色々な新しい言い方もありますが、彫刻という言葉で総体を指し示す事のほうが多いです。ただ、彫塑という言葉も、美術史の上ではちゃんと生きています。彫刻というのは木ですとか石を、例えばのみですとかたがねとかそういったもので上から彫っていく。かたまりを彫っていって、外のものをはじいて、中の像を造るのが刻。彫る方ですね。彫塑というのは、例えば人体でしたら、まず骨組みを作るんです。で、そこにシュロ縄を巻いて。このシュロ縄というものは滑り止めなんですけれども、その上に粘土をつけていくんです。で、たくさん付けすぎたなと思ったら、手やヘラでかき取る。で、また必要だと思ったら付けていく。
今は彫刻・彫塑とか色々な言い方が存在しますけども、これは全て翻訳語なんですね。明治の美術に限らず、いろんな文化の中の言葉というのは翻訳語がたくさんありますけれども、まあ美術という言葉もそもそもそうですけれども、彫刻という言葉も翻訳から生まれた言葉です。(右段に続く)
それで、長いこと彫刻という言葉が使われてきた時に、明治27年(1894)に朝倉文夫の先生だった大村西崖という美術史の先生が、みなは彫刻と言っているけどもこうした粘土で作る仕事というのは、彫刻と言うよりも塑像と彫る要素が両方あるのだから、彫塑と言った方がいいんではないかという彫塑論というのを書きます。朝倉はその先生に指導されていますし、そういうことで、自分のやっている仕事は彫刻ではではないんだ、自分は彫塑を作っている。自分は彫塑家だということを非常にありがたく、また大事にして、一生その自分の仕事と彫塑という言葉にこだわった人です。ですから、ここが今朝倉彫塑館、その前身が朝倉彫塑塾というふうに、彫塑という言葉がきちっと入っているのはそうしたわけですね。
Q: 朝倉は彫刻にも携わったのでしょうか。
朝倉は彫刻の技術も持っています。朝倉は明治30年代に東京美術学校で勉強するわけですけれども、その当時の彫刻家というのは彫塑を選択しても、必修科目で木彫の勉強もしなくてはいけません。その当時の木彫の先生は高村光雲です。天下の高村光雲ですけれども、光雲先生にきちんと木彫を習って、その上でというか、それに平行して、こういう粘土の仕事もやる。ですから技術的には、木彫の作品も現在は一点だけ残っていますが、小さなものでは石を削るというそうしたテクニックも朝倉はきちんと有しています。

Q: 大隈重信像についてはどのような経緯で作られたのでしょうか。親交はあったのでしょうか。
生前の大隈侯と朝倉文夫は個人的な付き合いがありました。どうも朝倉の人間形成や思想形成の上で、大隈重信という方が非常に影響を与えた、そういう節があります。恐らくそうした関係から、大隈重信像は3回造っています。現存するのは2点ですが、最初の作品は現存しないのですが、芝公園に衣冠束帯の最初の大隈侯の像を造っています。もうひとつは国会議事堂に置かれているフロックコート姿の像です。そして最後が、早稲田大学にある大隈侯の像です。当彫塑館にあるのは、その像の原型の複製です。原型は石膏原型ですが、展示していますと保存が厳しいので、今は別の素材に移したものを展示していますが。これが、もっとも有名な大隈侯の像であると思います。このような像は肖像彫刻と言います。一般に銅像という言い方が多いのですが、美術史上は肖像彫刻と言います。
朝倉文夫は、肖像彫刻を非常にたくさん作りました。500とか600体程も作ったと言われていますが、そのほとんどが注文を受けて作ったものです。大隈侯もそうした中のひとつですが、やはり朝倉文夫は大変なテクニシャンでしたから、なかなか上手く作るのですが、それでも芸術的と言うか創作の気分が乗って作った作品と、注文がきたから作ったという作品もあるわけです。気分が乗った作品と、その中でも特に内容の優れた作品があるのですが、この大隈重信の像はそうした意味でも内容が濃い作品と思います。ただ形、表情を写しとっただけではなく、彫刻という表現の難しさだと思いますが、ただそこにあるもの、人を写す。特に生きている肖像彫刻の場合には、その人の過去と現在と未来をひとつの中に収めなくてはいけないというのが肖像彫刻にはあります。たとえば俳優が2時間の芝居の中の一人の人物の何十年の生涯を演じるのを2時間で収めるというのは、これは一種の抽象化です。だけれども、美術家がある一点を作るというのは、ただその形を作ればいいのではなくて、過去と現在と未来をまとめる、そこの中に収めるということがどう上手くいくかということを背負っています。ですからそういう言う意味ではこの大隈侯の像というのは彫刻的に、そのような内容を有しています。それからやはりこれはただ立っている像を造ったのではなくて、色々な彫刻的な難しさがあるんですね。立っているバランス、それからポーズ、まっすぐ立っているのではなくて、これが少しひねられると全部体のひとつひとつに運動が起こっていく。このマントに包まれている体の中がどういう風に動いて一人の人間を立たせているのか、というようなことを解決しながら作っていくんですね。そうしたことが上手くできた、成功したという例です。他には肖像でいえば、ここに4点ありますけども、この4点はどれもそうした内容を持っています。特に團十郎の像や、それから父と母の像がありますが、これらは朝倉文夫の代表作と言っても良い作品だと思います。
Q: 大隈重信像は、実物よりずいぶん大きいようですが。
作品のサイズというのは、大概の場合は注文主の希望に沿うということが多いようです。小さい方が珍しく、まず等身で作ると事が基準です。朝倉文夫は近代の彫刻家と言いながらも、やはり古い日本というものを背負って作っていると思われます。この像は昔の言い方で言うと、一丈二尺というサイズです。これより大きくなると一丈六尺から一丈八尺というサイズになります。このようなサイズは、仏を作る仏師が丈六仏というような言い方をしますが、同様の仕様です。ですから、朝倉は木彫の光雲先生に習って、そうした古い木彫の世界と戦って新しい近代彫刻、彫塑を切り開いていった人ですが、やはりそういう古いものも同時に背負っていて、このようにサイズを決定していたようです。おそらく早稲田大学あるいは大隈候の顕彰会から注文があり、そのサイズを決定する時に、あの構内の台座の高さを何尺程にしましょう、そしてその上に乗る像は一丈二尺とした。一丈二尺というのは靴から頭の上までのサイズで、台座は含みません。その一丈二尺にしましょうと、そのようにして決定したサイズだと思われます。(次ページに続く)

朝倉彫塑館研究員の村山万介さん