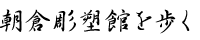Q: 彫刻家といえばロダンもそうですが、朝倉文夫との関連はあったのでしょうか?
朝倉文夫とロダンという比較は、近代彫刻史の中でよく取り上げられる話題です。これはなぜかと言うと、朝倉文夫は非常に古典的な、イタリアのアカデミックな基礎に則った仕事をした人だと言われます。朝倉のデビューした同時代にヨーロッパに留学して帰ってきた作家の荻原守衛や高村光太郎、この二人がロダンを本格的に勉強して帰ってくる。そうして日本に一種のロダニズムというものを紹介する。荻原や光太郎は、当時の現代美術であったロダンを紹介して、その一方、朝倉は良くない意味でのアカデミズムにまだしがみついている、表面だけの形を作り、ロダンのような内から盛り上がるような作品ではないというような、非常に単純な線引きをしていました。ただ調べていくと、朝倉文夫は確実にロダンを勉強していたという事が分かっています。それはロダンの作品を実際に手元においているという事からも分かりますし、何よりもたとえば代表作の墓守のモデリングというのが、やはりどこかロダンを勉強していないとあり得ない土の付け方をしています。それから卒業制作作品の「進化」でさえ、女性の像の足をスパッと切っています。これはトルソー的表現と言いますが、要するに全身が揃っていなくても、腕が欠けていても、また足が無くても、それ自体が彫刻として成立している事が大事というトルソーの表現を、卒業制作の時点で既に試みています。このような表現は突然そういう事を思いつくはずはないので、やはりロダンを勉強したからという事が分かります。他の作品を見てもそういう事が明瞭に分かりますから、朝倉はロダンを勉強していなかったという事は考えにくいですね。むしろ他の人よりもよほど勉強したんじゃないかというように思われます。
Q: 書棚に、マックス・ビルの、いわゆる抽象彫刻の蔵書が見えますが、朝倉文夫は抽象彫刻にも関心があったのでしょうか?
朝倉は確かにヨーロッパに留学せずに、日本で勉強した作家です。ただ、もう明治40年代は、ヨーロッパの新しい美術の情報というのはどんどん入ってきていましたから、光太郎や守衛は確かにパリでロダンを勉強したかもしれませんけれども、そういうことがなくても朝倉文夫のような感性やテクニックや観察力、そうしたものを持った作家でしたら、十分に当時の現代美術というものを吸収する事はできたと思いますし、それを表現として活かしていると思います。


Q: 猫を題材にした作品がいっぱいですね。
ここは猫の作品ばかりを集めて展示していますが、元々は東洋蘭のための温室だった部屋です。今ちょうど東洋蘭が咲いていますが、生前には400鉢程の蘭がありました。朝倉は本当に蘭が好きで、自ら東洋蘭の作り方という本まで書いている熱の入れようでした。(右段に続く)
朝倉はほぼ生涯に渡って、色々な時に猫を制作しています。もっとも早い時期の作品に「吊るされた猫」という作品がありますが、ほぼ生涯に渡って特に最晩年には、亡くなる年に猫百態展を企画して、100点の猫を作って大きな展覧会をやりたいと言っていました。その年(1964)は東京オリンピックが開催される年でしたから、そういうことに合わせて猫百態展をやりたいという、本人はそのつもりだったようです。ただ、その年の早い時期に朝倉は亡くなってしまいましたので実現せず、実際には50点程の作品しか残っていません。
朝倉文夫の作品を大きく分けますと、肖像彫刻がもっとも大きな部分を占めています。そして、もうひとつは展覧会に出品した創作作品です。等身大の男性像であったり、女性像があります。そしてもうひとつは展覧会に出品していますが、どちらかというと朝倉が本当に作りたかったものと言って良い、それがこれらの猫の作品かと思います。肖像彫刻はやはり注文がありますから、まず似ていなくてはいけないというような条件があります。創作は、特に若い時には賞を取らなければいけない、代表作という気概で出品しなくてはならないと、やはり背負うものがあります。けれども、これらの猫の作品では、そのような気負いがなく、写真も残っていますが、朝倉は猫が大好きで、10匹以上の猫を飼って、猫の動きというのはなんて美しいのだろうと、また猫が人の言う事を聞かないところも含めて、猫の気ままなところも好きだ等と言ってます。作品から、そうした気持ちが自然とすっと入っている、肩の力が抜けている、そこがかえって表現を自由にしていると思います。
朝倉は非常に厳しく弟子に基礎を指導した人ですし、自身も基礎を守った作り方をする人でした。そして厳格な写実をする人でしたが、猫ももちろん、猫からそのまま型を取ったんじゃないかと思いたくなるほどの描写をしています。たとえば筋肉の動きや色々な仕草について、言ってしまえばデフォルメという事にもなりますが、この猫も今まさに飛び上がってねずみを銜えて、この後飛び降りていくという一連の動作がこの中にと表現されています。けれども、この猫の姿に朝倉自身が気持ちを奪われている。そういうものまで入っている。集中していながら、彼の気持ちも実に楽しそうだというのが見ている側に伝わってきます。猫の作品はそのような意味で、朝倉の作品の中でも極めて興味のある、また、レベルの高いものだと思います。

Q: 習作の題材として猫を使っていたのですか。
私は、お嬢様の彫塑家の朝倉響子さんから聞いた事がありますが、膝に猫を乗せて撫でているのですが、あれはきっとお父様は猫の骨格とか筋肉の付き方を手で確かめていたのではと言われていました。非常に触覚の鋭い人でしたから、触れば手が覚えるわけですね。それを今度は彫刻に写していく時に、自分の手で変えていったという事でしょうね。(次ページに続く)