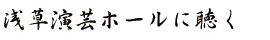屋根裏部屋について
ここは、昔ビートたけしさん(北野武氏)が寝泊まりしていた部屋です。ビートたけしがここに来た頃は、お金もなければ着る物もない、裸一貫で来ました。着るものもないものだから、楽屋の衣装を着ていた事もありました。窓もない部屋ですが、ここで連中は集まって車座になって1杯飲んで、また明日も頑張ろうってな事で頑張っていました。でもここ布団を敷けば2、3人は泊まれるから、いつも人がたむろしていました。

東洋館の舞台
ここが東洋館の舞台です。たけしが出ていました。
Q: 結構お客さんと距離が近いですね。満席になるとどの程度のお客さんが入るのですか。
お客さんとの距離は近いですね。だからやり易いのです。お客さんの顔が直に見えてね。ここは、200席あります。

Q: 昔の写真や絵葉書を見ると、このあたりは映画館が多かったようですが。ここと奥山はあまり縁がないのでしょうか。
ロック(六区)の映画館通りと言いました。通りの両側に映画館が沢山ありました。ここは、奥山から繋がっていました。エノケン(榎本健一氏)が最初に芝居をやったのは奥山です。
Q: 昔は近くに凌雲閣(浅草十二階)があったのですか。
凌雲閣はこの通りの突き当たりで、花やしきの並びにありました。今はパチンコ屋さんになってしまいました。この辺りも、高層ビルが建て込んでしまって、風景が変わってしまいました。
Q: 現在、浅草六区は再開発されているとの事ですが。
再開発というのか、色々な店舗や業種がどんどん進出していますね。パチンコ屋さんとか、ホテルだとか。明治から大正、昭和初めに掛けて、それから映画が寂れた頃の昭和35年(1960)頃と、六区は変わり続けています。
Q: 再開発を契機にして、浅草に来られた海外のお客さんもこちらまで誘導しようとされているのでしょうね。
そうですね。浅草を回遊してもらえれば良いのですが、一ヶ所だけでは駄目なんですね。色々なものが趣向を凝らしてあれば良いのですが。
Q: 江戸時代には、浅草寺に参って、帰りは奥山で遊んで帰られたのですか。
江戸時代には、浅草寺の先には猿若町があり、そこに歌舞伎小屋がありました。いわゆる猿若三座という小屋です。三座は大きい小屋ですけど、その他にも大小の小屋も入れて20軒程もあったと言われています。その奥に行くと吉原でした。芝居小屋があって吉原があって、あの辺が最も江戸時代は賑わった所だったのでしょう。(右段に続く)
Q: 元は、六区には瓢箪池があったという事でしたが。
瓢箪池の辺りは、元は沼地でした。浅草寺さんも、最初は駒形の、現在はどじょう屋さんの側に「こまんどう」(駒形堂)という小さな祠でした。その後に、天海大僧正が、上野の山、当時は日蓮宗の山だったんですけど、天海大僧正がここを天台宗の山にするという事にしました。その際に江戸城からみて浅草は鬼門にあたるという事で、浅草寺を駒形堂から現在の地に移しました。それが浅草寺の始まりですが、それ以来、浅草が賑わってきたのでしょう。明治時代になって浅草公園となり、それから七区に区画整理されて、芝居小屋があった頃、そして大正時代になり、浅草オペラの時代、そして活動写真の頃が最も賑やかな時代でしょう。この界隈も、弁士が忙しく往来していましたが、トーキーになり、弁士も多くは仕事を失いました。そして、エノケン(榎本健一氏)とかロッパ(古川ロッパ氏)が台頭してきて、笑いの王国という浅草を作りました。
Q: 三波伸介さん等は、まだ後の時代ですね。その前と言うと、てんぷくトリオの前ですから脱線トリオあたりですか。
ずっと後ですね、戦後ですから。脱線トリオ(由利徹氏、南利明氏、八波むと志氏)なんて、古いのによくご存知ですね。
Q:脱線の後がてんぷくで、その後はコント赤信号ですか。
コント赤信号もトリオでしたね。あの頃、コントというと、幾人かでやるのが流行った時期でしたから。大体トリオでしたね。あきれたぼういずが流行った時期ですね。あきれたぼういず(益田喜頓氏、山茶花究氏、坊屋三郎氏、そして芝利英氏、川田義雄氏)あたりが一世を風靡しましたね。
Q: 浅草演芸ホールでは、落語の他にはどのような演目がありますか。
ここは落語、漫談もあり、紙切り芸や太神楽(だいかぐら)等もあります。太神楽は、太神楽曲芸協会なんてのがあってね。
Q: こちらで養成されているのですか。
若手の養成は、国立劇場でやって頂いていますね。国立劇場にそういう三味線を弾く囃子さんだとか、曲芸等の養成を、国立劇場さんがやっています。ありがたいことですね。
Q: 国立劇場で勉強して、こちらに来られるのですか。
そうです、国立劇場で養成して頂いて、後にそれぞれの協会に配属して頂きます。これを国でやって頂いていますが、ありがたい事ですね。
Q: 芸の種類は、決められているのですか。
国立劇場に演芸場という小さな小屋があって、そこで三味線や太神楽だとか、伝統的な寄席芸を養成頂いています。
Q: 漫談や落語はないのですね。
そういうものはやりません。例えばうちに落語家になりたいと来る人がいますが、うちでは落語家を養成するというよりも、噺家は師匠に付かないと寄席に出れません。そういうしきたりになっていますので、師匠に紹介します。漫才やコントは、漫才協会や東京演芸協会等の協会がありますから、ある程度物になりそうだなっていう人は協会に入ります。