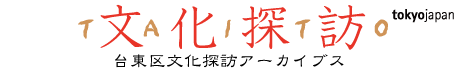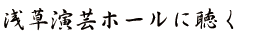Q: 私が通っていた頃は、落語では桂文楽さんや古今亭志ん生さんを聴いた記憶もありますが、漫才や漫談では、牧伸二さんや若手ではツービート、泉ピン子さん等の頃ですね。泉ピン子さんが、ギター弾いて漫談をやっていた記憶があります。
ビートたけしさん(北野武氏)の頃ですか。大分ずっと後の時代ですね。泉ピン子さんは、当時牧伸二さんのプロダクションに所属していましたからね。
Q: 浅草フランス座から現在の名前に変わったのは、いつ頃ですか。
浅草フランス座が、一時東洋劇場って名前に変わりましてね、それでフランス座が4、5階に移りました。下の階が東洋劇場で、上にフランス座がありました。フランス座は、たけしさんがいた頃、そしてその後もしばらくありましたが、後にフランス座は閉じて、下の階に寄席を、上の階は漫才とかコント等の小屋へと演目も次第に変わりましたね。
Q: こちらの古株は、やはり三波伸介さんや渥美清さんあたりでしょうか。
そうですね、三波伸介さんは、新宿フランス座が主でしたね。今、伊勢丹別館がある所に新宿フランス座がありました。当時、ムーランルージュという軽演劇の小屋があったのですが閉館してしまったので、ムーランルージュにいた三波伸介さん等が、うちに移ってきたんですね。
Q: 当時の芸人さんは専属制だったのですか。
当時は、専属制です。浅草フランス座は、渥美清さんが頑張っているものですから、三波伸介さんが入る余地がなかったんですね。じゃあ、お前は新宿に行けよという事で、新宿フランス座で南利明さんや伊東四朗さんと軽演劇等をしていました。
Q: 伊東四朗さんは、早稲田大学の生協職員だったという事ですが。
早稲田大学職員だという事で、伊東四朗さんが遊びに来ていましてね。私も舞台に上がりたいんだと言っていたんですが、その当時は舞台に上がる役者が勢揃いしていましたから、とても伊東四朗さんが出る場がないんですよ。そのかわり夜の内職でキャバレー巡りやるから、お前鞄持ってついて来いと言われて、それで何となく役者になったというわけですね。
Q: 浅草演芸ホールの館内をご案内頂けますか。
ここが楽屋です。(右の写真参照) こういう感じでございますな。ここに芸人さん達の着物を掛けておいてね。今、前座さんが今日の根多帳(ネタ帳)を書いてます。このように、毎日誰が何をやったかと前座さんが書くんです。前にやったネタは、後ろの人はやらないという習わしになっていますから。だから今日何をやろうかと決めてなくても出て来るんです。

Q : 寄席文字を使用されているのですか。
これは、前座さんが自分の字で書いています。表のめくりなんかは、勘亭流というか、寄席文字です。これは寄席文字専門の連中がおりましてね、その連中が書きますね。(右段に続く)

Q: こちらの楽屋は、出演者の皆さん全員で使われるのですか。
ここは昔は舞台裏だったんですが、楽屋として改装しました。ここは、噺家の楽屋で、いわゆる色物と呼ばれる漫才やコント等は、2階の楽屋を使っています。
Q: ここは、お囃子部屋ですか。お囃子は何人でされているのですか。
お囃子は、2人程来ておりますね。他は、前座さんが太鼓を打ったり、鐘を鳴らしたりします。

Q: 高座裏の文字は、何ですか。ネタですか。(下の写真参照)
落書きなんですよ、前座さん達が好きなように書いて行きますな。師匠方は楽屋に入りますが、前座や下っ端は楽屋に入れませんので、この辺で待機しています。ここにいれば、高座の話も聞けますから勉強になります。ロッカーも、前座さん達が使ったりしています。

2階の楽屋について
渥美清さんがここへ座って。そこの楽屋の台がそっちもずっとあったんですよ。鏡もずっと長く貼ってありました。それだけ大勢の役者がいたっていう事ですね。

Q: この2階の楽屋から1階に降りて舞台に出たのですか。
昔はここに窓がありましてね、窓から舞台が見えました。今誰が出ているやらと、そろそろ出番だとか、ここから見て楽屋を出ていました。
Q: 芸人さんは、楽屋入りはいつ頃されるのでしょうか。
おおよそ2、3時間前には入ります。忙しい売れっ子は、いやあ遅くなっちゃってとか、言い訳しながら飛び込んで来ます。
Q: 若手の方は東洋館の方に出演されているのですか。浅草演芸ホールと東洋館では客層が違うのでしょうか。
そうですね、浅草演芸ホールと東洋館を掛け持ちなんてのもいますね。東洋館に出て、そしてまた演芸ホールに戻って来るのがいますね。客層は、やはり違いますね。落語が好きな人は寄席に来ます。落語以外の、漫才とかコントの、いわゆる色物が好きな方は、上の東洋館に行きますね。(次ページに続く)