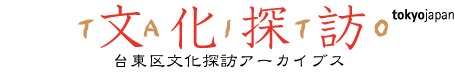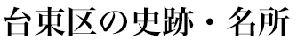01. 細井平洲墓(ほそいへいしゅうはか)
都指定旧跡
西浅草3-14-1 天嶽(てんがく)院墓地
細井平洲(1728〜1801)は江戸後期の儒学者です。諱は徳民、平洲・如来山人などと号しました。尾張国知多郡の農家に生まれますが、京都、名古屋に出て学び、長崎に遊学します。名古屋では折衷学派の中西淡淵に師事します。宝暦元年(1751)江戸に出て、嚶鳴館を開きます。西条藩邸や上杉邸に招かれ、上杉邸では世子の上杉治憲(後の鷹山)の訓育に当たります。治憲の家督相続後、米沢に招かれ賓師となります。鷹山の生涯の師と言われ、藩政改革の教学面を指導し、藩政改革、家臣団の統制の大きな役割を果たしました。その後尾張国名古屋藩主徳川宗陸にも招かれ、藩校明倫堂の督学となります。寛政4年(1792)、督学を辞し江戸に帰ります。享和元年(1801)6月29日、74歳で没します。

02. 石川啄木歌碑(いしかわたくぼくかひ)
西浅草1-6-1 等光(とうこう)寺
石川啄木は明治19年(1886)岩手県に生まれる。はじめ明星派(みょうじょうは)の詩人として活躍した。しかし、曹洞宗の僧侶であった父が失職したため一家扶養の責任を負い、郷里の代用教員や北海道の新聞記者を勤め、各地を転々とした。
明治41年(1908)、文学者として身を立てるため上京して創作活動に入り、明治42年(1909)からは東京朝日新聞の校正係となった。小説や短歌の創作に励み、明治43年(1910)12月には処女歌集『一握の砂』を出版する。生活の現実に根ざし口語を交えた短歌は、歌壇に新風を吹き込んだ。
しかし苦しい生活の中で肺結核を患い、明治45年(1912)4月13日に小石川区久堅町の借家で死去した(27才)。親友の土岐善麿(歌人・国文学者)の生家であった縁で、葬儀は等光寺で行われ、啄木一周忌追悼会も当寺で行われた。墓は函館市の立待岬にある。
この歌碑は、啄木生誕70年にあたる昭和30年(1955)に建てられた。『一握の砂』から次の句が記される。
浅草の夜のにぎはひにまぎれ入りまぎれ出で来しさびしき心

03. 山田宗徧墓(やまだそうへんはか)
都指定旧跡
西浅草1-2-16 願竜(がんりゅう)寺墓地
山田宗徧(1627〜1708)は、江戸時代前期の茶道家で、宗徧流の祖です。京都本願寺末寺の長徳寺住職の子として生まれますが、18歳の頃に千宗旦に師事します。茶道に一生を投じ、母方の姓の山田を名乗ります。宗旦の四天王筆頭とされます。宗旦は宗徧が26歳のときに京都鳴滝に草庵をかまえた折りに、利休伝来の四方釜を宗徧に与えます。宗徧の号、四方庵はこれに因みます。29歳のときに師に代わり、三河国吉田藩小笠原家の茶頭として仕えます。また、宗旦の不審庵、今日庵の号の使用も許されます。
元禄10年(1697) 、小笠原長重の老中補佐とし岩槻転封に際し致任し、江戸に出て本所二ツ目に四方庵を構えます。これが、江戸千家流茶の湯の礎となりました。宗徧は茶器の自作も多く、著書では『茶道便蒙鈔』『茶道要録』『利休茶具図絵』などがあります。

04. 織田得能墓(おだとくのうはか)
西浅草1-6-7 宗恩(そうおん)寺
織田得能は、明治時代の真宗大谷派の僧侶。わが国初の仏教の辞典『仏教大辞典』を著した人物として殊に著名である。
万延元年(1860)、福井県坂井郡波寄村(現福井市)の翫香寺(がんこうじ)住職である生田氏の三男として生まれる。郷里で教員を務めた後、真宗大谷派の高倉学寮で仏教学を修め、明治23年(1890)、島地黙雷(しまじもくらい)とともにインド・中国・日本の仏教史を述解した『三国仏教略史』を編纂し、翌年、宗恩寺第二十四世住職となり、織田性を名乗った。また、同33年(1900)には、岡倉天心とともに、インド・中国の仏跡を訪ねまわり、その見識を更に高めた。
『仏教大辞典』の執筆は、明治32年(1899)から得能が亡くなるまで、宗恩寺の土蔵の中でただ一人の力で続けられた。生存中には刊行されることはなかったが、大正6年(1917)、彼の原稿を元に、上田万年(うえだまんねん)・芳賀矢一(はがやいち)・南条文雄(なんじょうぶんゆう)・高楠順次郎(たかくすじゅんじろう)によって刊行され、後学に大きく貢献した。
彼の遺骸は、当寺境内の歴代住職墓に合葬された。平成6年(1994)10月には、得能の筆「念仏成仏」の四文字を模刻した頌徳碑(しょうとくひ)を建立した。

05. 佐野善左衛門政言墓(さのぜんざえもんまさことはか)
西浅草1-3-11 徳本(とくほん)寺
佐野善左衛門政言は、鎌倉幕府の御家人で「鉢の木」の逸話で著名な佐野源左衛門常世の子孫と伝えられる。
政言は天明4年(1784)3月24日、殿中桔梗の間で、時の権力者田沼意知(おきとも・老中田沼意次[おきつぐ]の子)に刃傷(にんじょう)におよんだ。意知は翌日死亡。政言も同年4月3日切腹し、28才で一生を閉じた。幕府の公の記録は「営中において発狂せり」と断定し、私怨とも記された。田沼の政治は積極的に幕府財政を立て直したが、利権との結び付きが強く、収賄など世の指弾を浴びていた。また天明年間(1781~1788)には飢饉、大火が続き、物価が高騰して、怨嗟の声が溢れていた。この刃傷事件の翌日から、高値の米価が下落し、老中田沼意次も失脚した。
徳本寺の政言の墓には「世直し大明神」と崇め、多数の老若男女が参詣した。この庶民の方が刃傷の真因を鋭く見抜いていたのである。これを脚色した歌舞伎の「有職鎌倉山」は有名で、以来、現在まで度々上演されている。

06. 宋紫石墓(そうしせきはか)
西浅草1-3-11 徳本(とくほん)寺
宋紫石(1716~1786)は江戸中期の画家。本姓楠本、通称幸八郎、字は雪渓、雪湖、霞亭などと号した。
宝暦年間(1751~1763)長崎に遊学し、清朝の画家沈南蘋(しんなんぴん)の精緻な写実画を受け継いだ熊代熊斐(くましろゆうひ)に学んだ。さらに宋紫岩の薫陶を受け、名を宋紫石と改め、遂に一家をなし、江戸に帰って、大いに南蘋派を流布させた名匠である。
南蘋派は日本の伝統画に写実の思想を再覚醒せしめた近代日本画壇の源流であるが、その代表が宋紫石で、その流れは宋紫山(しざん)、門人の司馬江漢(しばこうかん)、諸葛監(しょかつかん)、酒井抱一(さかいほういつ)、蛎崎波響(かきざきはきょう)などに受け継がれる。他に南蘋派の写実の甚大な影響を、葛飾北斎、渡辺崋山に与えている。なお、この写実に西洋画法を加えた面は、司馬江漢によってさらに発展した。
徳本寺の墓には、紫石とその子紫山、孫紫岡(しこう)が共に葬られている。またこの寺に、紫石の傑作が多数所蔵されている事は有名である。

07. 清水浜臣墓(しみずはまおみはか)
西浅草1-4-15 善照(ぜんしょう)寺
清水浜臣(1776〜1824)は江戸時代後期の国学者・歌人です。通称を玄長、泊洦舎(ささなみのや)、月齋などと号します。不忍池の辺りに居を構えていたため、泊洦と号したと言われます。医師道円の子として生まれ、医を業とします。村田春海に古学を学び、古学の研究で一家をなします。『万葉集考註』『伊勢物語添註』などの学書や、『泊洦文集』などの歌集、『県門遺稿』などの編著があります。特に旅行を好み、『杉田日記』『甲斐日記』などの紀行も残しています。

08. 伊豆長八の墓(いずちょうはちのはか)
松が谷2-1-2 正定(しょうじょう)寺
長八は鏝絵(こてえ)を描き、『異本日本絵類考』に、「最古の技に長ぜり」「柱等に種々に絵画を泥装するをもて、専門の業となし、また花瓶額面等に、花卉鳥獣の形を塗る、世人以て絶妙の技となす」と評された人物。鏝絵と漆喰を塗った上に、鏝で絵を描きだしたもので、石灰画ともいう。
文化12年(1815)8月5日、伊豆国松崎で誕生した。俗に伊豆長八と呼ばれ、世に知られた。天保元年(1830)に江戸へ出て、左官棟梁源太郎の弟子となった。修行のかたわら、狩野派の画法を学び、乾道と号した。また晩年には仏学も学んで天祐と号したという。明治3年(1870)に名字の名乗りが許されると、最初上田と名乗り、後に入江と改姓した。
明治22年(1889)10月8日に78歳で深川に没すると、遺骨は正定寺に埋葬され、同時に松崎の浄感寺にも分骨された。正定寺の墓石には、「入江家先祖の墓」と刻まれ、台石には「深川播摩屋」と養家の家号が刻まれている。

09. 島田虎之助の墓(しまだとらのすけのはか)
松が谷2-1-2 正定(しょうじょう)寺
虎之助は直心影流島田派の剣客。文化11年(1814)に豊前国中津(現大分県中津市)藩士、島田市郎右衛門親房の子として生まれた。10歳頃から、中津藩剣術師範堀十郎左衛門の道場で学んだ。上達が早く、数年後には藩内で相手になる者はいなかったという。16歳の春および翌年には九州一円を武者修行し、名声をあげた。
天保9年(1838)に江戸へ出て、男谷精一郎の内弟子となった。一年余で師範免許を受け、男谷道場の師範代を勤める。同14年(1843)、東北方面に武者修行の後、浅草新堀で道場を開く。その道場には、勝麟太郎(後の海舟)も通った。
虎之助は男谷につぐ幕末の剣豪といわれたが、嘉永5年(1852)9月16日に39歳で病没。墓碑には、「余、哀歎ほとんど一臂を失うごとし」と、男谷精一郎の銘文が刻まれている。

10. 玉川庄右衛門および清右衛門墓(たまがわしょうえもんおよびせいえもんはか)
都指定旧跡
松が谷2-3-3 聖徳(しょうとく)寺
庄右衛門・清右衛門の兄弟は、玉川上水開削工事の請負者で、江戸の町人と言われているが、その出身地は明らかでない。玉川上水の開削工事は、四代将軍家綱の承応2年(1653)1月13日に幕命が下り、2月11日に着工された。工事費として幕府から7,500両が下賜されたという。羽村から四谷大木戸に至る43キロの導水部は、承応3年(1654)6月20日に完成した。その後給水地域は順次拡大され、江戸城内をはじめ四谷・麹町・赤坂の高台などの山の手から、芝・京橋方面に及んでいる。現存する玉川上水は、江戸時代初期の土木技術の水準を今日に伝える貴重な文化財である。
近世都市江戸の水道施設建設の功績により、兄弟は200石の扶持を賜り、玉川上水役に任ぜられた。また玉川という名字を与えられ、帯刀も許された。兄の庄右衛門は元禄8年(1695)に、弟の清右衛門は翌年の元禄9年に死去した。明治44年(1911)政府は、玉川兄弟の功績に対して従五位を追贈した。
二基の墓のうち、向かって右側が庄右衛門の墓。笠付きの角石墓塔で、梵字の下に楷書で、「玉川本家先祖代々」とあり、さらに「隆宗院殿贈従五位正誉了覚大居士」の戒名が刻んである。
向かって左側が清右衛門の墓。先の尖った角石墓塔で、梵字の下に楷書で、「接取院殿贈従五位光誉照山大居士」の戒名が刻んである。両墓石は大正12年(1923)の関東大震災で破損したが、昭和12年(1937)、有志によって修復された。

11. 浅草三十三間堂跡(あさくささんじゅうさんげんどうあと)
松が谷2-14-1
『文政町方書上(ぶんせいまちかたかきあげ)』によると、寛永19年(1642)11月23日、弓師備後(ゆみしびんご)が浅草において、幕府から6,247坪8合の土地を拝領し、三十三間堂を創建した。位置はこの付近一帯と推定される。
堂創建に際し、備後は矢場(やば・弓の稽古場)を持つ京都三十三間堂にならい、堂の西縁を矢場とし、その北方に的場を設けた。ここでの稽古は京都の例にならって、堂の長さを射通す「通矢(とうしや)」の数を競った。
元禄11年(1698)9月6日、世に「勅額火事」と呼ぶ江戸大火が起こり、三十三間堂も焼失、跡地は公収された。同14年(1701)に替地を給され、三十三間堂は深川に移転して再建。以後、両者を区別するため、浅草・深川の地名を冠して呼ぶのが通例となった。
矢先稲荷神社は的場に隣接していたのにちなみ「矢先」の名が付されたという。

12. かっぱ寺の伝承(かっぱでらのでんしょう)
松が谷3-7-2 曹源(そうげん)寺
巨嶽山(こがくさん)曹源寺は曹洞宗に属し、天正16年(1588)に和田倉(現千代田区)に開かれ、後に湯島天神下に移り、明暦の大火(1657)の後、現在地に移転したと伝える。当時の通称を「かっぱ寺」という。
伝承によると文化年間(1804~1817)に、当地の住人で雨合羽商の合羽川太郎(かっぱかわたろう・合羽屋喜八)という人物がいた。この付近は水捌けの悪い低地で、雨が降ると洪水となり、人々は困窮していた。そのため、川太郎は私財を投じて排水のための堀割工事に取り掛かった。この時、かつて川太郎に助けられた隅田川の河童が工事を手伝い、堀割工事が完成した。この河童を目撃すると商売繁盛したという。
この伝承が「かっぱ寺」という通称の由来であり、「合羽橋」(合羽橋交差点の付近にあった)という橋の名もまた、この伝承に由来するともいわれる。
当寺には河童大明神が祀られる他、合羽川太郎の墓と伝える石碑があり、「てつへんへ手向けの水や川太郎」という句が刻まれている。

13. 梅田雲浜墓(うめだうんぴんはか)
松が谷3-3-3 海禅(かいぜん)寺
雲浜は名をはじめ義質、のち改めて定明といった。通称源次郎。雲浜は号である。若狭国小浜(おばま・現福井県)藩士、矢部岩十郎の二男として、文化12年(1815)6月7日生まれ、後に祖父の生家梅田氏を継いで改姓した。
朱子学を修め、大津、京都で子弟を教える。嘉永5年(1852)、幕府を批判したため小浜藩を追放される。しかし藤田東湖(ふじたとうこ)・佐久間象山(さくましょうざん)・高杉晋作らと交際し、尊王攘夷論を唱え、梁川星厳(やながわせいがん)とともに在京志士を指導した。その活動は常に幕政批判で、開国論者の大老井伊直弼排斥も企てたが、安政5年(1858)の「安政の大獄」で捕らえられた。翌6年9月14日、小倉藩江戸邸の獄中で病没。遺体は海禅寺内の泊船軒に仮埋葬され、文久2年(1862)現存の墓石が建てられた。墓石は関東大震災で大破したが、正面に「勝倫齋俊巌義哲居士」と、戒名が刻まれている。

14. 合羽橋跡(かっぱばしあと)
西浅草3-7-2
この地点西方の合羽橋交差点の所に、橋が架けられていた。合羽橋である。橋梁台帳によると、昭和8年(1933)廃橋になったが、長さ約4メートル、幅11メートルの橋だった。橋下の水路は新堀川・新堀といい、南流して鳥越川に合していた。
寛文11年(1671)刊の絵図に描かれているものの、創架年代は不明。初め無名橋で、のち橋畔の寺院名をとって清水寺(せいすいじ)橋といい、ついで合羽橋と呼んだ。近くに合羽屋があったので、合羽橋といったそうだ。文化年間(1804~1817)、合羽屋喜八、通称合羽川太郎が私財を投じ、隅田川に住む河童の助けを得て、新堀を開いたとの伝承がある。橋名由来はその伝承に因むともいう。
橋が繋いだ東西に伸びる道は合羽橘通りと呼ばれ、江戸初期から浅草・上野を結ぶ主要路として賑わい、今日に至る。昭和44年(1969)10月まで、合羽橋は都電停留場名になっていた。

15. 日輪寺(にちりんじ)
西浅草3-15-6
神田山芝崎道場日輪寺という。創建は一説に9世紀、武蔵国豊島郡芝崎村(現千代田区大手町)に、天台宗の了円法師が開基したと伝えられる。芝崎村には天慶の乱で天慶3年(940)に戦死した平将門の項墓が築かれたが、のちに荒廃して、将門の亡霊が村民を悩ますようになった。嘉元年中(1303〜1306)、時宗二祖他阿真教(たあしんきょう)上人が村人の求めにより丁寧に供養して亡霊を鎮め、その霊魂を神田明神に祀った。村には平和がたちまち戻り、上人は村民たちに請われて日輪寺を時宗の念仏道場に改めたという。江戸時代の神田明神祭礼では、日輪寺の僧侶が読経してから神輿を出す例となっていた。
日輪寺は天正18年(1590)徳川家康の江戸入城以後、江戸の都市整備や災害復興などにともない、何度か所在地を変えている。現在地に移転した年代は二説あり、慶長8年(1603)という説と、明暦3年(1657)江戸大火の後という説がある。
明治2年(1869)から昭和40年(1964)まで、この付近の町名を芝崎町といったが、その町名は日輪寺に由来している。

16. 岡崎屋勘六墓(おかざきやかんろくはか)
西浅草1-7-19 清光(せいこう)寺
いわゆる歌舞伎文字である勘亭(かんてい)流の祖。勘六は、号を勘亭と称し、延享3年(1746)江戸に生まれる。堺町(現中央区日本橋)に済み、御家流の書を指南して能書家として知られていた。
勘六は、安永8年(1779)中村座の依頼を請け、従来の浄瑠璃正本の文字などを参考に春の狂言の大名題を書いた。これが、歌舞伎文字勘亭流のはじまりとされる。以来、中村座の看板を書きつづけ、その独特の書風は鳥居派の芝居絵とともに世に流行し、天明年中(1781〜1788)からは勘亭流といえる一家の書法として公表。文化2年(1805)59歳で没するまで、もっぱら劇場のための看板や番付の執筆を業とした。
勘亭流は、御家流の書風に様式化を加えたもので、現在もこの伝統は継承され歌舞伎看板などで使われている。
墓石裏面には
ありがたや心の雲の晴れ渡り
只一筋に向かう極楽
と、勘亭流で刻まれている。