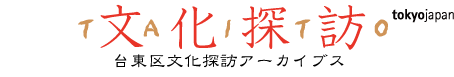地図作成に用いられた製図道具一式
日本地図編纂に大きな貢献を果たした伊能忠敬は、下総国佐原(現千葉県)の伊能家の家業興隆に精を出す傍ら、数学・測量・天文などを研究し、漢詩・狂句も良くし、子斉と字し、東河と号しました。五十歳の時に家督を譲り、江戸に出て高橋至時の門に入り、西洋暦法、測図法を学びました。寛政12年(1800)に幕府に願い出て蝦夷地(現北海道)東南海岸の測量に着手して以来18年間、全国各地を測量して歩きました。しかし、地図未完のうちに文政元年(1818)に七十四歳で没しました。
地図作成はその後幕府天文方に引き継がれて、没後三年の文政4年(1822)に「大日本沿海輿地全図」として完成しました。この地図は、「日本輿地全図」、「実測輿地全図」とも称されますが、俗に「伊能図」とも言います。伊能忠敬の墓は、源空寺墓地(台東区東上野)にあり、墓石には「東河伊能先生之墓」と刻まれています。師の高橋至時は、文化元年(1804)に四十一歳と若くして没し、墓は源空寺にあり、墓石には「東岡高橋君墓」と刻まれています。伊能忠敬は、師の側に葬られる事を願って遺言としたとのことです。(参考:たいとう名所図会)

中型象限儀
象限儀は測量のための観測器具。伊能忠敬の師である間重富が「霊台儀象志(南懐仁等撰、1674)」などを参考にして作らせた天体の角度測定器です。象限儀には、1/4円形状の半径6尺の大型象限儀と半径3.8尺の中型象限儀があり、全国測量には中型が用いられました。
星座之図[複製](文化10年(1813))
高森観好(1750-1830)が描いた、天の川も加えられた独特の彩色による星図。観好は、器物製作に長けていて、オクタント(八分儀)、象限儀、温度計、天文時計などの多くの科学器械を残しています。平賀源内が修理・製作したエレキテルなども、独自に製作したと伝えられています。

高森観好(1750-1830)が描いた、天の川も加えられた独特の彩色による星図。観好は、器物製作に長けていて、オクタント(八分儀)、象限儀、温度計、天文時計などの多くの科学器械を残しています。平賀源内が修理・製作したエレキテルなども、独自に製作したと伝えられています。


中型象限儀
象限儀は測量のための観測器具。伊能忠敬の師である間重富が「霊台儀象志(南懐仁等撰、1674)」などを参考にして作らせた天体の角度測定器です。象限儀には、1/4円形状の半径6尺の大型象限儀と半径3.8尺の中型象限儀があり、全国測量には中型が用いられました。