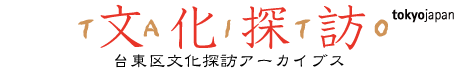池本 : 地球館(新館)のこのフロアでは、日本の科学技術の発達の歴史について展示しています。日本は明治維新以降、西洋の科学技術を取り入れて飛躍的な発展をしました。そして今日、私達は世界でも有数の科学技術立国として、その恩恵を受けて生活しています。しかし、西洋の科学技術を受け入れる以前の江戸時代の人々が独自に生み出した科学技術がその根幹にあり、これらが西洋の科学技術と融合して、現在の科学技術に結びついたのです。

小方儀(しょうほうぎ、江戸時代後期)
伊能忠敬が、全国測量の際に「わんからしん」と読んだジンバル構造の方位磁石。方位磁石を載せた杖をどのように傾けても、水平がとれるようになっています。
このコーナーでは、江戸時代の天文学と測量の技術について、展示をしています。江戸時代にも多くの土木治水や鉱山の開発などが行われてましたが、このような事業は正確な測量技術や天文観測の技術などによって支えられていました。こちらは当時の天文学の資料なんですが、当時、江戸の初期までは、日本の暦というものは中国から輸入したものでしたが、幕府の天文方によって貞享暦という暦がつくられ、それから日本独自の暦を使用するようになりました。こちらの展示が、地球儀や天球儀など当時の天文の教育等に使われた物です。
こちらのコーナーでは、測量技術について展示しています。測量といえば、伊能忠敬を思い浮かべますが、これは伊能忠敬が使った象限儀の復元模型です。測量をするためには天体を正確に観測することが非常に重要で、このような道具を用いて天体を観測しながら測量を行っていました。伊能忠敬は千葉県の佐原市の実家で家業を続けながら、測量や天文の勉強をしていました。50歳の時に高橋至時(よしとき)の弟子になり、西洋の測量術や天文学の勉強を始めました。そうして、1800年から16年の間、全国を縦横に渡り歩いて測量をして、このような日本地図を作成したのです。こちらが伊能忠敬が測量に使った量程車と言って、これを引っ張って車輪の円周の長さを歯車の運動に変えて距離を測っていました。ただし、当時の道路の状況や、動輪の誤差を加えると、これでは正確な測量は出来なかったのではと考えられていますが、測量をこのようにしていますよというアピールをするためにこのような物を使ったのかもしれません。その当時にも、西洋からも様々な測量の道具が入ってきて、このような測量の参考書なども出回って見られるようになりました。(右段に続く)
こちらは、測量の道具類です。測量したデータを縮図に落とし込む製図用の道具です。こっちは測量するための縄ですね。縄を引っ張って、二つの地点の間の距離を測るもので、一間(約1.82メートル)毎に目盛りが付いています。このような測量の道具を使って、日本全国を測量して回っていました。測量といっても、もちろん伊能忠敬一人で出来るわけではありません。測量に回った土地で、地元の人たちの力を借りながら測量していったと思われます。このようにして伊能忠敬等が日本全国を回りながら測量するにつれて、その土地々々で基礎的な算術や計算などの知識を有する人々がいたと言います。それだけ日本全国に寺子屋などの、当時の教育システムでそのような教養を身に付けた人が多くいたことが、このような大事業を成し遂げた基礎になっているのだと思います。

見盤(複製)
見盤上に目標物との相似三角形を作ることでその高さを測ることが出来ます。

江戸時代の暦(上)、日本経緯度実測表(下、複製)
伊能忠敬が行った経緯度観測の成果。緯度については、象限儀を用いて当時でも高い精度で観測を行うことができ、経度については「水揺球儀」という振り子時計を用いています。水揺球儀では、日差が数分となることもあり、伊能忠敬はほとんどの経度の測定に失敗しています。本書でも経度については数地点が記録されるのみです。

大和七曜暦(複製)
七曜暦は、日々の太陽、月、五星の動きを記述した天文暦の一種ですが、室町時代に途絶えていました。江戸時代に渋川春海が行った貞享改暦において再度用いられるようになり、本書は、天和3年(1683)の七曜暦。江戸時代末期まで製作されました。

小方儀(しょうほうぎ、江戸時代後期)
伊能忠敬が、全国測量の際に「わんからしん」と読んだジンバル構造の方位磁石。方位磁石を載せた杖をどのように傾けても、水平がとれるようになっています。